出船型
(読み)でふねがた
(意味)船首を海側に向けること
私の地元は、船の運輸で栄えていた時期がありまして。
海運ではなく、川運ですね。江戸から明治のころまででしょうか。
今となっては、そんな面影はないのですが。
歴史に詳しいマニアックな人が、そのわずかな痕跡を知る程度です。
普段は、そんなことまったく気づかずに、生活しています。
そんな歴史もあってか、お酒の席で、とある翁から「出船型」について聞いた記憶が。
船首は、次の出発時に出やすいように考えて、着岸させておく。
転じて、自分の履き物、靴のつま先は外に向けておくと良い、という意味合い。
他人の履き物も、玄関やトイレなどで向きを揃えて出やすいように、という心配り。
社会人として、次のことを考えてあらかじめ準備しておくことの重要性、そして、
他人に対して、さりげない気遣いができることが大切だよ、ということを学びました。
私も「向きが整っていると、気持ちが良いな」と感じるので、誰も見ていない時は、ついつい
他人のスリッパであっても、揃えて「出船型」にしてしまうクセがついちゃいました。
ただし、レアケースですが「消防や救急などの人の靴は揃えないで」という話も聞いたことが
あります。なぜなら「プロは自分で出やすい形にして覚えているから」だそうです。
他人に向きを変えられてしまうと、小さな親切・余計なお世話、になってしまうのですね。
また、料亭で下足番(お客様の靴を収納する係の人)がいる時は、入船型がマナーだとか。
なぜなら、下足番の人のお仕事をとる行為になるから、だそうです。
(でも下足番の方がいる料亭なんて、そんなに行く機会はないよ、って気もしますが。)
まぁ、そもそも「出船型」の考え方は、知らなくても普段の生活ではまったく困りません。
でも、知っているだけで、人間の営みの深さと言うか、趣と言うか、知恵と言うか、
そういうものを感じることができます。
日本に生まれ育って、そういう機微に思いを致すことができて、幸せだな~と思います。
4月、新たな船出、皆それぞれが、それぞれの目的地へ、出港~。

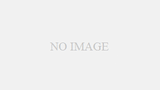
コメント